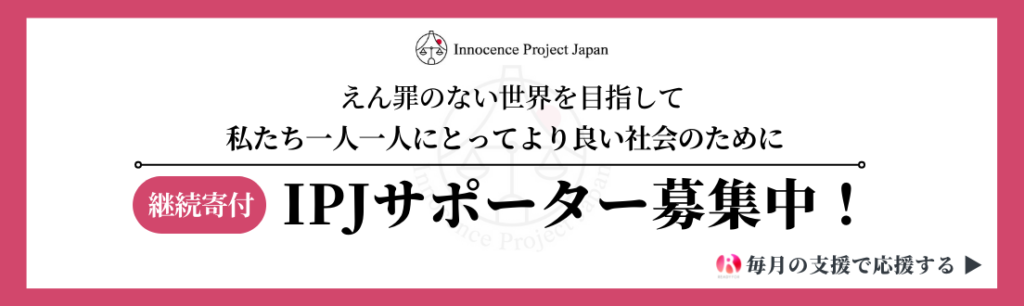名古屋研修1日目は名古屋地方検察庁を見学して、検察の仕事や日本の刑事制度について学ぶことができた。
最初に検察官の方から説明を受けた。検察が起訴・不起訴を判断する存在であることは知っていたが、改めて話を聞くと、警察と連携した捜査や裁判での立証など、複数のはたらきをしていることがわかる。制度として理解していた知識が、実際の運用のイメージと結びついたことで検察の仕事をより深く知ることができた。ニュースなどで「検察が起訴した」という場面を耳にすることはあっても、その裏側には社会の秩序や人権を守るための責任ある仕事があることを理解できた。
庁舎見学では、取調べに使われている部屋に入ることができた。ドラマや映画で見るものと似てはいたが、実際にその場に立つと空気が全く違っていて、かなり緊張感があると感じた。机と椅子が向かい合うだけのシンプルな空間だったが、被告人にとってはもちろん、えん罪で疑われた人にとっても大きな重圧を感じる場所なのだろうと思った。
手錠や腰紐、警棒なども実際に触った。ニュースや写真では見たことがあっても、自分の手で重さや硬さを体感するのは初めてだった。特に手錠は想像以上に重く、これをつけられることで自由が奪われる重みを実感した。器具を通して、刑事手続きが現実に人の身体や生活に大きな影響を与えることを改めて考えさせられた。
さらに、取調べの可視化についても説明を受けた。えん罪事件の原因として、「密室での取調べ」がよく問題にされてきたが、現在では録音・録画による可視化が進められているとのことだった。これにより被疑者の人権が守られるだけでなく、検察側も取調べの正当性を示せる点で意義が大きいと思う。ただき、まだすべての事件で義務化されているわけではなく、今後さらに広がっていく必要があるとも感じた。
今回の見学を通して、検察の働きが社会にとってどれだけ重要かを実感すると同時に、権力の行使と人権保障のバランスを取ることの難しさについて考えるきっかけになった。教科書で読むだけではわからない「現場の空気」に触れられたのは、とても貴重な経験だったと思う。
(甲南大学3回生・F.Y)
研修のいっかんとして、名古屋地方検察庁に行きました。
検察庁を訪問するのは初めてで、取調べが実際にどのような場所で行われているのかを見学できるというのは非常に楽しみでした。
はじめに、検察庁の仕組みや業務内容について検察官から説明を聞いた後、実際に取調べが行われている部屋を見ました。その後、実際に検察事務官が身に着けている服や、所持している手錠などを触らせていただき、最後には質問にお答えいただきました。
検察庁の役割は、適正な捜査手続を通じて、刑事事件の真相解明を行い、罰すべきものは起訴し、犯した罪に見合った刑罰が科されるように公判活動(裁判)を進めていくというものです
令和5年の被疑事件の処理状況は、起訴(公判請求・略式命令請求)が36%、不起訴(嫌疑不十分・起訴猶予)が45%であり、不起訴処分の方が多いです。
検察庁に置かれている取調室では取調べが行われます。取調べの内容を録音録画できるように、カメラが設置されています。具体的な取調べの内容は、検察官が被疑者の前で口述し、その内容を横にいる検察事務官がパソコンで打ちこんだ後に、印刷をしてそれを読み上げます。このようにして供述調書が作成され、被疑者はその内容を確認して間違いがなければ署名押印します。その様子を説明いただきました。
普段見ることのできない取調室は思っていた以上に広く、椅子も検察官のものだけは豪華だったので驚きました。
戒具を見させていただいた時には、警棒や手錠などを触ったり実際に使ってみたりしました。警棒は小さいですが重く、手錠は手にかけられると本当に何もできなくなってしまうなという圧迫感がありました。
今回の検察庁訪問を通じて、録音録画を徹底し、適正な取り調べ・捜査を行ってほしいと感じました。貴重なお話を聞き、実際に感じた経験を今後に活かしていきたいと思いました。
【甲南大学一回生・清水晃生】
1日目に名古屋地方検察庁を見学した。普段ニュースなどで耳にする「検察」がどのように活動しているのかを実際に知ることができ、貴重な体験となった。
まず、職員の方から検察庁の業務について説明を受けた。検察官は、警察の捜査結果を法的に適正にかつ十分なものかどうかを吟味し、起訴の可否を判断する。また公判では、収集された証拠や証言をもとに事実認定を導き、社会に対して犯罪の存在を立証する責任主体となる。私たちの生活の中では直接かかわる機会が少ないが、法秩序を維持するためには欠かせない存在であると感じた。
その後、取調室を見学した。取調室内は想像していたよりも質素で、机と椅子が向かい合って配置されていた。ニュースやドラマで目にする取調べの場面を思い浮かべていたが、実際の部屋はとても緊張感のある空間であった。取調べを録音・録画するための装置が備え付けられていた他、通訳者の席も設置されており、日本語が話せない被疑者にも配慮されていた。
その他にも、手錠や腰縄、警棒にも触れさせていただいた。手錠は想像していたよりも重く、手錠と腰縄両方を実際に装着してみることで、装着される側にとっては身体の自由が効かなくなってしまうため、強い拘束感があるのだろうと感じた。警棒も実際に手にしてみるとずっしりとした重さがあり、使用は最小限に限られるべきものであることを改めて理解した。
今回の見学を通じて、検察庁の業務は単に「事件を処理する」ものではなく、社会の安全と公正を守るために冷静かつ慎重な判断を積み重ねる仕事であることを強く感じた。取調べの録音・録画の導入はえん罪を防ぐために欠かせない仕組みであり、一人一人の権利を守る視点が不可欠であると感じた。これまで検察という存在を遠いものと考えていたが、私たち市民の生活や安心に直結する役割を担っていることを理解できたのは大きな収穫であった。今回の体験をきっかけに、法や社会の仕組みをより主体的に学び、自分自身の進路や生き方にも生かしていきたいと考えている。
(甲南大学3回生・K.A)