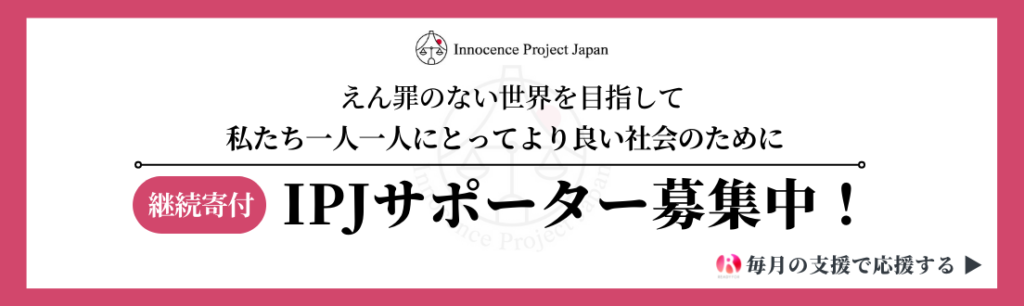映画「オレの記念日」の上映会に参加しました。
「オレの記念日」は、20歳の時に冤罪により殺人犯とされ、29年を獄中で過ごした、いわゆる「布川事件」の桜井昌司さんの半生を描いたドキュメンタリーです。作品中には罪を犯していないのに不合理な国家権力によって人生の大切な時間を奪われた1人の男性の生き様が記されていました。
桜井さんは29年かけて無罪判決を勝ち取り、その後も冤罪事件で苦しまれている方々に会いに行ったり、冤罪について知ってもらうための街頭演説を行ったりするなどして冤罪被害者の支援を行ってきました。自分の事件だけでも相当な精神力をすり減らし、裁判所や冤罪に関わりたくないと思っているはずなのに、過去の自分と同じような境遇の方々への支援を行っている姿に感銘を受けました。またそのような活動の中で冤罪被害者の袴田巌さんに初めて会いに行き、袴田さんに「あなたは誰だ、私には関わらないでくれ 」といった言葉を言われた際に、諦めずに支援し続け信頼を得ていく姿にも「私もこういった生き方をしたいな」という感情を抱きました。
ドキュメンタリーを見て桜井さんの生き方に感激するとともに、桜井さんに関わらずなんの罪も犯していない無実の人の人生を長期間にわたって奪う可能性のある日本の刑事司法の現状に憤りを覚えました。
現在の日本では、やり直しの裁判である再審は「開かずの扉」と言われ、再審を開始するには非常に厳格な要件を満たす必要があります。刑事訴訟法435条6号は判決で一度確定した有罪をもう一度考え直すべきことが明らかな新証拠を発見したときに再審請求が認められると規定しています。他にも再審請求を行う方法はありますが、現在行われている再審請求の多くはこの要件に基づいて行われています。現在、事件に関する証拠は捜査機関である検察官 が所持しています。証拠を弁護人が調べなければ前述のような要件を満たすことが困難であることは言うまでもありません。それにも関わらず、刑事訴訟法には検察官の証拠開示を義務付ける規定は全くないのです。特に再審請求の際には裁判所が検察官に証拠開示勧告を出さなければ証拠を開示しないことが多くあるのですが、裁判所も法的安定性の確保が重要として再審に積極的ではありません。このような現状から、冤罪であるにもかかわらず再審請求するための新証拠を見つけるまで長期間獄中に閉じ込められる人が少なからずいます。
IPJが支援する神戸質店事件の冤罪被害者である緒方秀彦さんもその1人です。今後そのような人を1人でも減らすために、これからも活動を続けていきます。
【甲南大学法学部2回生 溝端一登】
======
ドキュメンタリー映画「オレの記念日」について視聴するイベントに参加しました。この映画は、布川事件と呼ばれる、1967年に茨城県で起こった殺人事件の犯人と疑われ、無実であるのに実刑判決を受けた冤罪被害者の桜井昌司さんの半生を描いたものです。桜井さんが無実の罪で刑務所に入り、その後、外の世界に出てからの半世紀の活動や体験が記録されていました。
布川事件は、桜井さんを含む2人の自白しか、有力な証拠がありませんでした。そのほかは、信用性が低い目撃証言や、証拠価値が低い物的証拠だけでした。自白についても、取調べで無理やり取られたものだと、裁判が始まってから桜井さんらは主張しました。1968年から1978年までの10年が経過しましたが、結果は無実の人が無期懲役を言い渡されることとなりました。10年の間に控訴と上告も棄却され、刑が確定しました。桜井さんは刑務所の中からも冤罪であると主張して再審請求をしましたが、認められませんでした。19年後に模範囚として仮釈放されるまで、計29年間を身体拘束されました。
仮釈放されてからも、桜井さんたちは、冤罪ということを主張し、殺人犯という汚名を晴らすために、活動していました。桜井さんは出所してから恵子さんという女性と出会い、ご結婚され、それからは夫婦二人三脚で冤罪であることを主張し続けました。
それまでの活動が実を結び、2回目の再審請求の2005年9月11日にようやく再審請求が認められ、再審の公判が開始されることが決定されました。その後も検察官による不服申立てで再審開始の確定まで長期化しましたが、2011年5月24日、事件から約44年後に、桜井さんら2人が60代半ばにして無罪判決が下され、20歳の頃から着せられていた殺人犯という汚名がようやく晴れました。
桜井さんは、冤罪を世間に知ってほしいという想いや、同じ苦しみの最中にいる人たちを助けたいという想いから、「冤罪犠牲者の会」を設立して、全国を駆け巡り様々なイベントに登壇したり、他の冤罪被害者のところへ赴いて、励ましたりしていました。桜井さん自身も、獄中生活の中で冤罪について少しでも知ってもらうために、詩集や歌、手紙や物語など多くの書物を自分の手で残していました。そして、イベントに参加した来場者に向けて、自らの歌や自分が体験してきた事などを織り込み語りかけました。
桜井さんは、活動の最中の2019年にステージ4の直腸がんと診断され、病体に鞭打ちながらも、冤罪被害を訴えること、冤罪被害者の方たちを励ますことをやめることはしませんでした。
桜井さんは、インタビューの中で、「真犯人が目の前に現れたら」という質問がされたとき、「大変だったね」と言うと決めていますと言いました。
自分も若い頃はやんちゃをしていた。過去の生き方は変えられないと割り切っている、だから、今さら変えられないことを言っても仕方がないというのです。
「自分は不運だけど、不幸ではない」。桜井さん自身、確かに無実の罪を着せられたことは不運であり、失ったものも多くあるが、人生で失ったものを嘆いてもどうしようもない。得たものを良かったものとして生きていくことが大切である。とにかく楽しく生きていこう。刑務所に比べたら、どんなことも楽しい。冤罪に遭ったことで会えなかった人に会えたし、経験することがないことを経験できた、と。だから、桜井さんは、冤罪になった自分が幸運だと思うから、警察に御礼を言いたい、自分は珍しい人だと思うと笑いながら言っていました。
この考え方に、私は衝撃を受けました。私は冤罪というのは、とても残酷で冷徹で、絶望で目の前が暗くなってしまうもので、あってはならないものだと考えてきました。桜井さんは、真逆の意見でした。もちろん桜井さん自身、冤罪は許されるものではないと考えているからこそ、上記の冤罪被害者の会を設立したり、冤罪を受けないようなシステムを作るために生きている限り頑張り続けるとおっしゃっていました。だから、私は、これからも冤罪に対する不条理に怒りを感じ、その感情を胸に秘めて将来の仕事への向き方を決めていきます。しかし、桜井さんのような考え方や生き方は、いつか自分が挫折や苦しい思いをした時に、励みになるし、元気を与えてくれると考えます。桜井さん自身が亡くなるまで続けた支援が、これからも未来に向かっても生き続けるだろうと思いました。
【甲南大学2回生・貴志純宇】
映画「オレの記念日」(2022年) 金聖雄監督作品