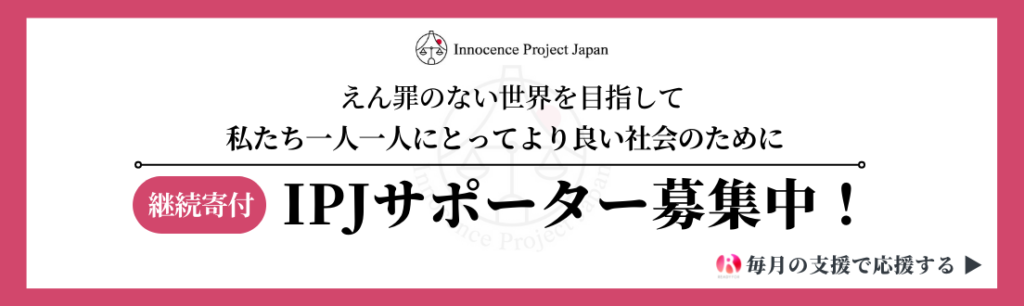2025年9月4日に、明石市にある神戸刑務所の参観に行きました。
はじめに、職員の方からパワーポイントで施設についての説明があり、その後に施設内を実際に見て回りました。会議室に戻ってからは、10名程の刑務官の方々と准看護師などの現場の方にも来ていただき、学生とグループに分かれて意見交換や質疑応答などを行いました。学生からの多くの質問に丁寧に答えていただき、刑務所のことだけでなく、刑務官というお仕事についても理解が深まる時間になりました。参観後は刑務作業製品(CAPIC)の即売所に行き、商品を実際に手に取ったり、購入したりしました。
神戸刑務所の敷地面積は、甲子園球場の約4倍ととても広く、所内には刑務作業を行う各種工場、寮、グラウンドなどがあります。受刑者の生活する区域は高い塀で囲われており、出入口は1つです。出入りする際には、2枚の扉を通らなければならず、その扉は2枚同時に開かないようなっています(逃走事故防止のためだそうです)。収容定員は1800人で、現在は約1200人が収容されているとのことでした。
神戸刑務所に収容されているのは、主に2回以上の犯罪歴がある人で、中には最低限の日本語ができる外国人受刑者も1割ほどいるそうです。覚せい剤取締法違反の受刑者が最も多く、被収容者の平均年齢は51歳、最低年齢は21歳、最高年齢は86歳だそうです。
施設の参観では、工場(金属、自動車整備、木工)と、収容棟の内部を見ました。工場では、受刑者がひとりひとりに与えられた仕事を黙々とこなされていました。刑務所内の工場で作る製品は、外部の会社の下請けだけでなく、神戸刑務所独自の製品を開発・製造したりもするそうです。製品開発の発案を受刑者がすることもあると聞きました。受刑者が刑務作業を通して物作りに携わることは、達成感や充足感をもたらし、社会でまともに働いて生活していく第一歩となり得るのかなと感じました。収容棟では、共同室と単独室に実際に入りました。居室内には、トイレ、棚、机など最低限のものだけが置かれていました。テレビもあり、余暇時間にテレビを見て過ごす受刑者の方もいるそうです。
今回、神戸刑務所を訪問するにあたって、私も含め学生の多くが「拘禁刑(※1)に処せられた者に対する処遇」について気になっていたと思います。その点についても、職員の方に教えていただきました。神戸刑務所では、矯正処遇課程(※2)として、受刑者の特性に応じて処遇の重点事項を類型化したものを8課程実施しています。そのなかで、「高齢者」「知的障害・発達障害」「精神障害」「依存症」への対応に力を入れているそうです。また、すべての受刑者を対象とした一般改善指導に加えて、特別改善指導として薬物依存離脱指導や暴力団離脱指導、性犯罪再発防止指導などを特定の事情を有する受刑者を対象に行っているそうです。
今回の参観では、刑務官の方々のお話をお聞きする機会が多くありました。お話の中で、刑務官の方が、拘禁刑の施行を受けて「受刑者との対話」という点により力をいれていらっしゃる事も学びました。出所後の円滑な社会復帰のために神戸刑務所が以前から設置しているハローワークシステムは、受刑者が出所後の生活への希望を持てるだけでなく、健全な社会生活を送るきっかけとなり、再犯防止にとても効果的だと感じました。こういった取り組みがより広く行われ、更生の意思を持つ受刑者への支援が社会的にもさらに受け入れられてほしいと思いました。
実際の現場に行き、刑務官の方の話を聞いて、学校で学んだ知識が深まっただけでなく、今まで知らなかったことを知ることができました。この経験を今後法律について学んでいくうえで生かしていきたいと思います。
※1 刑法等の一部を改正する法律(令和4年6月13日成立)により、懲役と禁固を廃止、新たな刑として拘禁刑が創設されました。(令和7年6月1日施行)
懲役・禁固では、刑務作業が刑の本質とされ、改善更生や社会復帰のために必要な指導を行う時間の確保が困難な場合がありました。一方拘禁刑では、個々の受刑者の特性に応じて、刑務作業・改善指導を柔軟かつ適切に組み合わせて実施します。
※2 受刑者の特性に応じた処遇を効果的・効率的に実現するために、処遇の重点事項を類型化した24課程が設けられています。
【甲南大学法学部・1回生N・A】
=========
2025年9月に、兵庫県明石市にある神戸刑務所へ施設参観に伺いました。神戸刑務所は、刑期を終えてから再度罪を犯してしまった、いわゆる累犯者と呼ばれる方々を主に収容している施設です。施設内には刑務作業を行うための工場がいくつもあり、受刑者の方々は黙々とご自身の作業に取り組んでおられました。見学後にはグループワークで少人数に分かれ、刑務官の方々に数多くの質問に答えていただき、様々なお話を聞くことができました。
刑務所を参観させていただいたことで、学問を学ぶだけでは知ることのできない現場での対応や取り組みについて学ぶことができました。2つ紹介します。
まずは、懲役刑と禁錮刑が2025年6月1日から拘禁刑へ移行したことによる受刑者の処遇の変化についてです。拘禁刑が導入されたことで、受刑者の処遇は個々の特性に応じて、作業、改善指導及び教科指導を柔軟に組み合わせて実施することになりました。以前よりも社会復帰のアプローチに種類を持たせ、そのアプローチが各人にあったものとなるよう試行錯誤が続けられているとのことでした。懲役刑で義務とされていた刑務作業は、拘禁刑では義務とはされておらず、改善更生や社会復帰のための「手段」となっています。矯正処遇過程の変化によって刑務所には柔軟な対応が求められています。拘禁刑が施行されて間もないこと、神戸刑務所が累犯者を中心に収容している施設であることから、施設参観日当日には神戸刑務所に拘禁刑を科された受刑者はおらず、試行錯誤は今後、続けられるものと思われます。
次に、社会復帰の取り組みについてです。神戸刑務所にはハローワークシステムがあり、それを活用することで出所後の円滑な社会復帰が見込まれます。協力雇用主との連携や、職業訓練による自動車整備士などの資格の取得など、社会復帰への過程は充実しているようでした。高齢受刑者の収容率が高まっていることから、地域の医療・福祉等の専門家からの支援が得られるネットワークや、高齢受刑者にみられる心身機能認知症傾向の対策と出所後の支援のための自治体との協力体制の構築など、現在の社会に応じた対応も取られており、受刑者のことが非常に考えられていると感じました。
刑務所には厳格な規律があり、刑務官の受刑者への接し方も高圧的なのだろうという先入観がありました。確かに、刑務所内の規則は決して緩くはなさそうでした。しかし、お話を伺うと、実際には考えていたよりも自由があることにも気づきました。受刑者の人権に配慮しているとのことでした。受刑者への制限もそうですが、接し方についても、現在は受刑者は「◯◯さん」と呼ぶなど、刑務官の中で人権配慮の意識が顕著になってきているようです。
刑務所などの施設へのイメージは、ドラマや書物によって構築されることがほとんどだと考えます。先に述べた私のイメージも昔ながらの刑事ドラマによるものです。しかし、その考えは実際の刑務所とは乖離していました。今後もIPJボランティアの学生の1人として活動していく中で、まずは私自身が偏見をなくし、事実を発信していきたいと考えました。
【甲南大学2回生・永湯将】