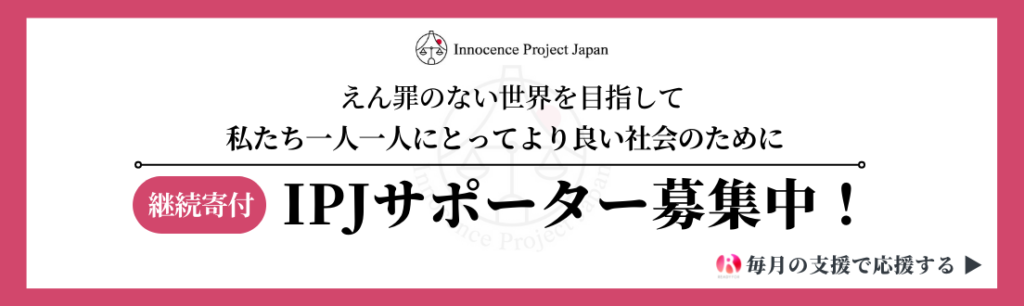2025年9月11日(木)に京女IPJ学生ボランティアが奈良少年院での施設参観を行いました。
最初に、少年院の現状や役割についての説明をしていただき、在院者数の変化や最近の在院者の傾向、教育活動の内容等について詳しくお話をうかがいました。
その後の施設内見学では、在院者がかつて使用していた寮を見学用に作り替えて、生活している部屋の様子を再現しているところや、木工科・窯業科・農園芸科の職業指導活動の場を見せていただきました。
また、日常の食事の内容や学習活動についても紹介していただきました。
質疑応答の時間には、見学を通して感じた様々な疑問に対して答えていただき、理解を深めることができました。
参加した学生からは、以下のような感想がありました。
初めに目に飛び込んできたのは、welcomeボードでした。木でつくられた大きなヒマワリに「welcome」と書かれていて素敵な作品で嬉しく思いました。それが、少年院にいる少年が制作したものだと知り、驚かされました。まだ奈良少年院の入り口までしか足を踏み入れていなかったのですが、少年院にいる少年たちは、非行などと負のイメージではなく、まだまだ秘めている才能があったり、これからの可能性であふれていると感じました。
特に印象的だったのは、性格に合わせて教育方法(農業と陶芸)を分けているということでした。見学する前は、半強制的に少年を矯正するために行っているというイメージがありましたが、少年の性格に合わせて農業や陶芸をしていることや実際にその場所を見て、これまでの矯正が強い教育ではなく柔軟さも必要で、少年が社会復帰できるように、矯正教育を残しながらも柔軟な教育が行われているということを知ることができて良かったです。
見学をして印象に残ったのは、更生教育の多様性と実践性です。特に陶芸や育児体験といったプログラムは、単に技術や知識を身につけるだけでなく、他者への思いやりや社会生活に必要な感覚を養う工夫がなされていると感じました。また、陶芸では、土を成形し作品を完成させる過程で集中力や忍耐力が培われ、完成品を手にすること、そして実際に販売まで行っていたりすることで、少年たちの達成感を得る姿が想像できました。一方、育児体験では、乳児の人形を用いた演習を通じて、命の重みや親としての責任を疑似体験できる点に教育的意義を感じました。実際、退院すると親になる少年もいると伺い、これらの活動は、少年法が掲げる「健全な育成」の理念を体現しており、単なる矯正ではなく、社会復帰後の生活力や倫理観を涵養するものであると理解しました。見学を通じて、法学部生として更生教育の実際を理論と結び付けて考える貴重な機会となりました。
少年院は、当初もっていたイメージとは違い、職員の方が在院者一人一人と向き合っていらっしゃること、少年たちが職業経験を受け、様々なことを学ぶことができる、前向きな施設であることがわかりました。今度、在院者の作った野菜や陶芸作品を買ってみたいと思いました。
今回の参観を通して、少年院の役割や教育の内容について学ぶことができ、とても貴重な経験となりました。
(京都女子大学1回生 Y・K)