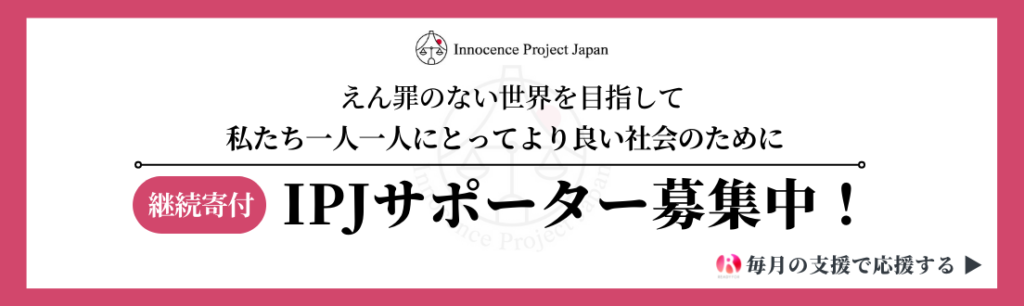三畳一間の独房は無機質で、太陽は一切見えない。入浴は週2回、運動も毎日決められた時間の30分間のみと決まっている。常に監視される生活、家族や大切な人たちとの連絡も絶たれた。孤独と自己嫌悪、無力感に苦しむ山岸氏に検事はこう語りかける。
「最終的にはなんらかの有罪って言われるかもしれないけれども、できる限りさくっと終わるような形にすれば、次のステップに行けると思うのよ、わたしは。」
つまり有罪を認めれば短期間の裁判を経て執行猶予判決になると示唆する、不正な利益誘導であった。この言葉が日本の「人質司法」を象徴していることを、山岸氏はのちに身をもって知ることとなる。
逮捕・勾留という非現実感と孤独感
株式会社プレサンスコーポレーションの社長を務めていた山岸忍氏は2019年12月16日、横領容疑で逮捕された。全く身に覚えのない容疑で逮捕されたことが信じられなかったが、何かの間違いだったと判明してすぐに拘置所から出られると信じていた。そのときはまだ検察庁が「真実」を追求する「正義」の組織だとおもっていたから。
弁護人との接見は1日1回1時間、当初は家族や大切な人たちと直接連絡を取ることもできなかった。一方で検察官からの取調べを毎日6~8時間受ける中で、孤独から救ってくれる存在として検事を信用するようになっていった。
従業員や取引先、株主を守るために、2019年12月23日、山岸氏はプレサンスコーポレーション社長を辞任した。辞任の夜は寂しさと悔しさのあまり、寝付けなかった。同時期に、部下が交通事故にあって命を落としたとの知らせも入った。自分のせいだ。こんな事件に巻き込まれて心労がかかりすぎたからに違いない…。自己嫌悪と無力感、そして日に日に大きくなる孤独感と戦っていた。
当時を振り返って、山岸氏はこう語る。
「閉じ込められた状態で長時間取調べが続くなか、検察官の言うことに自分の真の記憶通り『違います』と反論し続けるのは、すさまじい気力と根気がいる。これはきっと、逮捕勾留されたことのある人間にしかわからない。」

Photo by hiwamariin
人質司法という理不尽
同年12月25日の起訴後は、保釈請求を提出しては裁判所に却下される日々が続いた。無罪を証明するには勾留に耐えて、より多くの証拠を検証してもらわなければならない。
当時、部下と取引先社長の供述が本件横領事件への山岸氏の関与を裏付けていた。これらは担当検事による巧みな誘導や威迫による取調べによって得られた虚偽供述であることが後日明らかになったが、2人は起訴後すぐに保釈されている。一方の山岸氏は、家族や弁護人とも自由に会えず、太陽を見ることすら許されない。無罪を主張し、防御を一番に必要としていたはずの人物は、拘置所の中の「人質」だった。
取調べ中に検事からかけられた言葉をふと思い出す。
「最終的にはなんらかの有罪って言われるかもしれないけれども、できる限りさくっと終わるような形にすれば、次のステップに行けると思うのよ、わたしは。」
あのとき虚偽の供述をして罪を認めていれば、すぐに保釈してもらえたのかもしれない。全く身に覚えもない罪を認めていれば。
自由も名誉も財産も奪われて、拘置所の中からでは何もできないまま、時間だけが過ぎていく。このまま廃人になってしまうのではないか、そんなやり場のない憤りや焦燥感を、面会に来た家族や弁護人に思わずぶつけてしまう。長期間の拘留は山岸氏の心身、そして山岸氏を支える人々の心を確実にむしばんでいた。
虚偽供述をした者達は保釈され、証人を取調べで威迫した検察官が「山岸は罪証隠滅をするおそれがある」という意見を述べ続け、裁判所もそれを信じて、無罪を主張する私が閉じ込められ続けるという理不尽。検察庁は真実や正義を追求することよりも、組織として有罪を勝ち取ることしか考えていないのだと実感した。それならば、日本の刑事司法に期待して戦い続けることに何の意味があるのだろう。山岸氏は弁護人に何度も訴えた。
「はやく裁判はじめてください。」
「これ以上、勾留を長引かせないでください。気が狂いそうになります。」
絶望の中で力を振り絞り、ついに保釈が認められたときには、逮捕から実に248日が経過していた。
山岸氏は、保釈後の2021年11月に無罪が確定した。大阪地検特捜部が作り上げた冤罪事件であった。大阪地検特捜部は、同冤罪事件後も現在に至るまで、何らの原因究明や再発防止策を講じていない。
無罪確定から2年、山岸氏は人質司法サバイバーとして刑事司法手続の改善を訴えている。
「わたしは運がよかった。しかし、運がなければ冤罪を晴らすことのできないような国であってはならない。」
参照:山岸忍『負けへんで 東証一部上場企業社長vs地検特捜部』(文芸春秋、2023年)