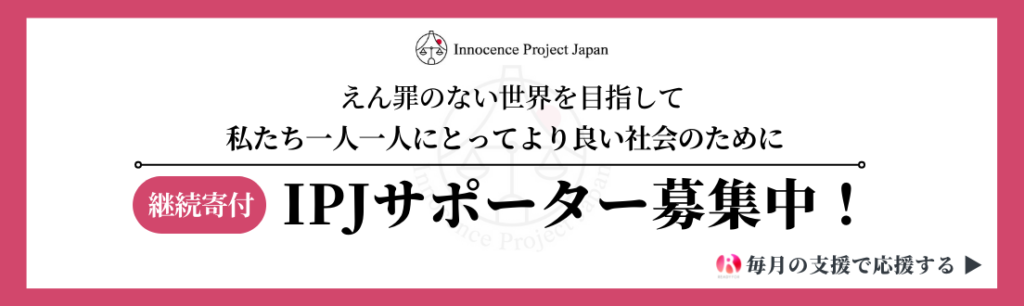IPJの8年間を振り返るコラム第2回では、2017年4月17日に発行された「えん罪救済センターNEWS」のNo.4から、「新年度のご挨拶」と題した記事をご紹介します。当時のセンター代表・稲葉光行(現在はIPJ科学者ネットワーク委員長)によるもので、センター設立までの経緯が記されています。
また、この号には、「科学的証拠とわが国の刑事裁判ー夜明け前・DNA鑑定との戦い」(佐藤博)、「『平野母子殺害事件』差戻後控訴審判決に思う」(木谷明)、連載「科捜研とは何だったのか 第1回」(平岡義博)といった記事が掲載されていました。
新年度のご挨拶

「えん罪救済センター(Innocence Project Japan,通称:IPJ)」が2016 年4 ⽉1 ⽇に発⾜してちょうど1年が経過した。この1 年の間に、⽇本の刑事弁護を代表する弁護⼠の先⽣⽅、著名な刑事法学者、法⼼理学者、法科学者など数⼗名が参加する専⾨家集団が形成された。IPJ は、ニューヨークのイノセンス・プロジェクトから「Innocence Project」という名称使⽤を許可された⽇本初の団体となり、⽶国や台湾のイノセンス・プロジェクトとの間での国際的な連携も進みつつある。国内外のマスコミでも取り上げられ、現時点での相談件数は2百件を超えている。海外ではロースクールに拠点を置き、実際に関わる専⾨家は数名というプロジェクトが多い中で、⽇本は「専⾨家が数⼗名」と答えると、その規模の⼤きさに驚かれる。発⾜後まだ間もないこともあり、雪冤までは⾄っていないが、特にIPJ 運営委員の先⽣⽅の多⼤なご助⼒によって、体制づくりという点においてはIPJ はかなりの成果を挙げたと考えている。
思い起こせば、技術屋の⽴場から志布志事件や⿅児島強姦事件の検証に関わり、そこで刑事司法の「科学性」に疑問を持った私は、浜⽥寿美男先⽣からのアドバイスもあって、IPJ 設⽴の約1年前(2015 年3 ⽉)にニューヨークとカリフォルニアのイノセンス・プロジェクトを訪問した。帰国後、指宿信先⽣、佐藤博史先⽣、笹倉⾹奈先⽣、平岡義博先⽣など錚々たる⽅々にお会いしたところ、「ずっと⽇本でイノセンス・プロジェクトを⽴ち上げたいと考えていた」というお⾔葉をいただき、そのような動きさえ把握できていなかった⾃分の無知を恥じるとともに、とにかく先⽣⽅が集まるハブ的な場を⽤意する⽀援をさせていただきたいということを申し上げた次第である。これまでIPJ の構想を練ってこられた先⽣⽅の⻑年の蓄積と知⾒がなければ、IPJ 発⾜後わずか1年でこれだけの体制が整うということはなかったということは明らかである。
IPJ 発⾜後に、私⾃⾝が驚いたことの1つは、その社会的な反響の⼤きさである。はからずもIPJ 代表として指名された私は、新聞社やテレビ局から多数の取材を受けることとなった。そこで何⼈もの記者から、「刑事司法を科学の視点から検証する組織ができるということは画期的です」と興奮気味に⾔われた。また、イベントを開催する度に、多くの市⺠の⽅々が集まり、寄付もいただけるようになった。結局⼀般市⺠としては、専⾨知識はなくとも⾃動⾞や⾶⾏機事故の原因調査といったプロセスはわかるが、様々なえん罪が明らかになる中で、司法判断の基準やプロセスはよくわからないという疑問があったのではないかと考える。そのような中でのIPJ の発⾜は、ある意味でタイムリーであったのかもしれない。
とりあえずIPJ は、体制作りと社会的な反響を得るという点においては、多くの先⽣⽅のご尽⼒や市⺠の⽅々のご⽀援もあって、⽐較的スムーズに滑り出すことができたと考える。しかしIPJ 本来の使命である科学的検証による雪冤活動という点においては、依然として⼤きな壁が⽴ちはだかっているように思える。実際、これまでの相談に対する検討の過程で、証拠へのアクセスが制限され、証拠保存も不⼗分な中で、⼗分な科学的証拠を⼊⼿することは不可能であるという結論になることも何度もあった。その結果、せっかくご相談をいただきながら、⽀援ができないという回答をせざるを得なかった⽅々には、IPJ の呼びかけ⼈の⼀⼈として⼤変申し訳なく思っている。
⽶国や台湾では、刑事裁判に関わる証拠の保存や保管について政府レベルでの審議が⾏われ、DNA 再鑑定を⽀えるための法制度なども整備されつつあると聞く。幸いIPJ は発⾜当時より、国際的な連携を重視してきた。従って今後は、個々の依頼案件を最先端の科学の視点で洗い出す作業をすすめながら、同時に海外の先進事例を紹介することで、⽇本の司法制度をメタな視点から検討するための情報提供や問題提起をしていくことが必要であろう。司法の現場で直接戦うことができない私⾃⾝としては、IPJ を通して、外部のメタな視点から、⽇本の司法の改善に多少なりとも貢献ができれば幸いだと考えている。またIPJ の先⽣⽅には、私のような司法の素⼈にも根気強くご教⽰をしていただきながら、同時に、司法の外の⼈間の視点を活⽤していただければ幸いである。