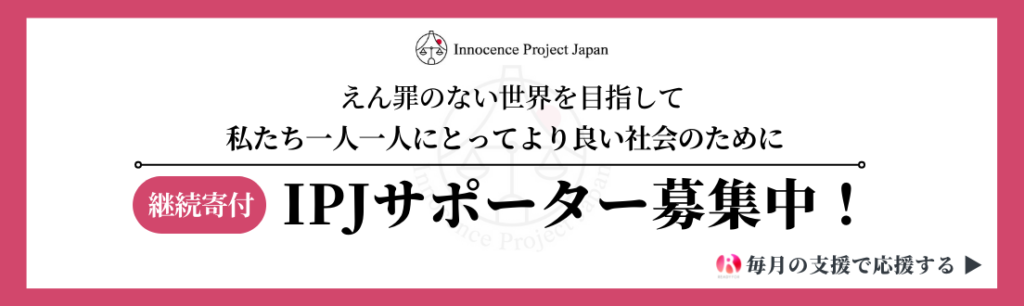私たち甲南大学IPJ学生ボランティアは、4月中旬、甲南大学で神戸質店シンポジウムを開催しました。IPJが支援している神戸質店事件を通じて日本の再審制度の問題点について広報することを目的とするもので、当日は学生が事案の詳細を説明し、弁護団の先生方をお招きしてパネルディスカッションも行いました。
パネルディスカッションでは、学生の質問に弁護団の先生方が答えるという形で行いました。実際に先生方の考えを聞くことで、神戸質店事件についてさらに深く学ぶことが出来ました。日本の再審制度の実態についても知ることが出来ました。日本では、再審に関する刑事訴訟法の規定が少なく、検察官に証拠開示をさせるか否かが裁判官の裁量にゆだねられていることや、裁判所の再審開始決定に対する検察官の異議申立てが認められており、手続の長期化を招いていることなど、多くの問題があることを学びました。
シンポジウムの準備を数か月間かけてするにあたって、初めてこの事件を知る人がいかに分かりやすく、理解できるものにするかを意識しました。
先生方への質問を考える際には、常に法律の知識が全くない人の立場になって考え、使用する法律用語は一般の方でも理解できるものか、質問の流れはおかしくないか、などに気を配りました。この活動を通じて、相手の立場になって考えるという経験から多くのことを学びました。今回の活動が多くの人に認知され、少しでも再審法の規定の改正に貢献できればうれしい限りです。
今回シンポジウムを開催するにあたって神戸質店事件の当事者である緒方秀彦さんからお手紙をいただきました。証拠がとても弱いのに、1人の人間の人生を奪ってしまう日本の司法制度に疑問を抱くと同時に、緒方秀彦さんの気持ちを考えると胸が張り裂けそうになりました。今後同じような状況に置かれる人を1人でも減らすことができるよう、活動を続けていきたいと思います。【甲南大学法学部2回生・溝端一登】
ーーーー
2025年4月19日に、甲南大学で神戸質店事件開催したシンポジウムは、甲南大学のIPJ学生ボランティア2、3回生が中心となって企画、準備、運営しました。
神戸質店事件とは、第一審では無罪判決が言い渡されていたのに、控訴審では逆転有罪となってしまったIPJの支援事件で、現在は再審請求に向けて準備が進められています。逆転有罪判決の決め手のひとつになったのは目撃証言で、一審では重要視されていなかったのに、控訴審で重視されたことによるものだと考えられます。しかし、私は初めて事件について勉強した時から、「控訴審判決は『有罪ありき』なのではないか?」と疑問に思ったことを強く覚えています。
本シンポジウムにて、私は事件の概要を説明しました。この事件を初めて知る方にも事件自体の流れ、そして問題と考えられるのがどのような部分なのかをわかりやすく説明するために、事件自体の流れを私自身がしっかり勉強し、理解することからスタートしました。一審と控訴審の判決文を読み勉強を進めていく中で、いくつかの問題点にも気づきました。まず目撃者に対する面割(事件の目撃者らに複数の人物の写真を見せて、その中から選んでもらう捜査手法)が適切に行われていないこと。そして、一審と控訴審で事実認定には同じ証拠が使われたにも関わらず判決結果が変わっていること。更には、一審判決が「犯人と断定するには合理的な疑いが残る」として無罪と判断したにもかかわらず、控訴審が証拠の評価を変えることによって「一審は誤った判断であった」として有罪であると判断したことに関しては 、疑問を超えて憤りを感じました。そのうえで「この事実を多くの人に知ってもらいたい」という気持ちで準備を行い、本番に臨みました。
一学生として、多くの参加者の方に本事件について知って頂けたこと、えん罪事件という大きな社会問題について考えられたこと、そしてそのような機会をシンポジウムに参加することによって得られたことはとても貴重な経験であったように感じます。参加してくれた知り合いの方から、「このようなえん罪事件が本当にあるとは知らなかった」や「えん罪についてあまり考えたことなかったけど興味が湧いた」といった意見をいただき、そもそもえん罪という問題自体を知ってもらうことがどれだけ大切なことなのかを改めて認識しました。今後も、本シンポジウムのように多くの方に私たちの活動、そしてえん罪事件について知り、考えて頂くための活動を続けていこうと思います。【甲南大学法学部2回生・KK】
ーーーーー
神戸質店事件はイノセンス・プロジェクト・ジャパン(IPJの支援事件のうちの一つで、IPJは神戸質店事件の再審請求を目指して活動しています。今回のシンポジウムは甲南大学の学生が主に準備・運営を行いました。神戸質店事件は2005年10月18日午後6時から午後8時30分に発生した事件です。事件現場は神戸市内の質店で、同店経営者が頭部を数回殴られて殺害され、現金1万650円が奪われた強盗殺人事件です。
この事件の現場には、緒方さんの足跡や指紋の跡などがあったとされました。しかし、緒方さんは電気関係の仕事をしており、以前に事件現場に入ったことがありました。したがって、これらだけでは緒方さんが犯人であるとは言えません。
緒方さんが有罪判決を下されたもっとも主要な根拠となったのは、事件当日に、事件現場で緒方さんを見たという目撃証言でした。
第一審は、目撃証言の証拠としての価値は低いとして無罪判決を言い渡しましたが、控訴審ではこの目撃証言が犯人性を認定する決め手となる証拠と評価され、有罪判決が言い渡されました。しかし、目撃証言には、証拠としての信用性が不十分な点がありました。例えば、目撃者は事件が発生してから1年10ヶ月後の面割で緒方さんの写真を「事件当日に見た人物だ」と示しました。事件が発生してから1年10ヶ月が経過しているのにこの供述が信用できるのかという点や、証言が変遷している点に問題があります。このような点を指摘し、目撃証言の証拠としての価値が低いことがないと判断されれば、緒方さんは犯人とはいえないはずです。
私はこの活動に参加してこの事件を調べることで、冤罪について考えるようになりました。私は一回生の頃に、ゼミで袴田事件のことを調べて発表しました。この事件での当事者の袴田巌さんが冤罪をかけられた原因として、警察の見込み捜査や自白を強要するような悪質な取り調べ、証拠の捏造などがあったと言われています。人間の過ちによって、袴田さんは誤った死刑判決を言い渡され、58年もの間、自由や尊厳を奪われたのです。
神戸質店事件でも、緒方さんに有罪判決が言い渡されたのは、人間の過ちがかかわっているのではないかと感じることが多くありました。この事件は第一審判決と控訴審判決で、証拠の捉え方が全く違いました。目撃証言だけでなく、第一審判決では重要視されなかった、指紋、足跡、たばこの吸い殻のDNA、緒方さんの借金などが、控訴審判決では全て有罪を示す証拠とされました。そこに私は、違和感がありました。冤罪が作られる根底には幾つもの人間の過ちがあるのかなと感じました。人間なら間違えるという行為をすることは仕方のないことなのかもしれませんが、人間の過ちによって冤罪をかけられた人は、自由も時間も社会的な地位も奪われてしまうのです。それは、理不尽や不憫という言葉では表現できないような事ではないでしょうか。
私はこれからもIPJでの活動を続けます。緒方さんや、緒方さんのような人の小さな小さな力になるために。【甲南大学2回生 NN】
ーーーーーー
シンポジウムには弁護団の方々や心理学の専門家である厳島行雄先生にもお越しいただき、パネルディスカッションなどを通じて多くのことを学ぶことができました。
神戸質店事件は2005年10月18日に発生した事件で、当該質店の経営者が頭部を多数回殴打されたことにより亡くなられ、現金1万650円が強奪された強盗殺人事件です。この事件で起訴されたのが、現在も無実を証明するために闘っておられる緒方秀彦さんです。
当該質店には緒方さんのものとされる足跡や指紋が残っており、また目撃者の証言からも犯人は緒方さんであると断定されました。緒方さんは仕事の関係で当該質店に出入りしたことがあり、足跡や指紋が事件発生当時についたものとは断定できない点、目撃者の証言が回数を経るごとに異なっており曖昧である点などから、第一審では無罪判決となりました。しかし第二審では、第一審では重要視されなかった目撃証言や足跡等が決定的な証拠として有罪判決に至りました。
この事件についてみなさんはどう思われるでしょうか。第一審と第二審では証拠に関する裁判官の判断が完全に逆になっています。問題となっている目撃証言や指紋等も曖昧であり、犯人であると断定するには疑問が残ると考えられます。このような信用性の薄いものを証拠として考えることは正しいことなのでしょうか。
今回のシンポジウムは、私にとって再審制度について考える機会となりました。再審制度は不当に有罪となってしまった人にとっては唯一の逆転の手段です。しかし再審請求をするには無罪であるとする「明白な新しい証拠」を発見する必要があるなど、容易ではありません。法務省が司法統計年報に基づいて作成した資料によると、令和2年の再審請求事件のうち、再審開始が決定した事件はありません。また、平成29年から令和3年の間、最高裁でも高裁でも再審決定はされていません。再審請求、そして再審決定に至るまでの道のりが険しいことを学ぶことができました。
神戸質店事件以外にも「おかしいのではないか。」そう思える事件は世の中には数多く存在します。私たち学生ができることは多くはありません。しかし、今後もIPJの一員としてまずは私自身が冤罪についての理解を深めていき、そしてシンポジウムなどの活動を通してより多くの人に日本の刑事制度、裁判の実態を知ってもらえるよう活動を続けていきたいと思います。【甲南大学2回生・NS】
引用元 https://www.moj.go.jp/content/001405738.pdf