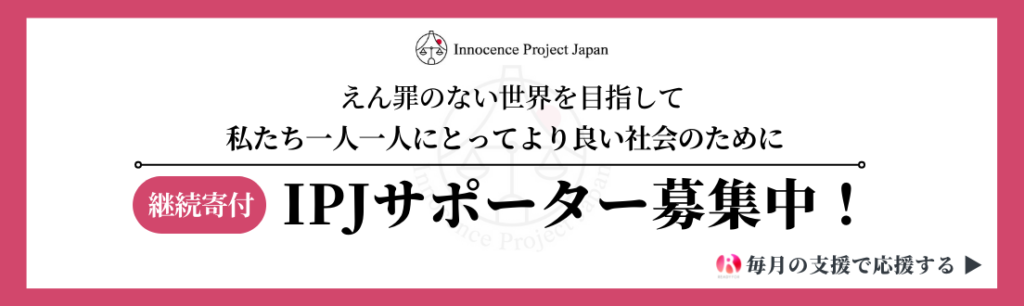「牢屋に入っている人=犯罪者」という漠然としたイメージが、一般の方にはあるかもしれない。このことは、ニュースで見る「逮捕された人=犯罪者」という認識になってしまうことともつながっているかもしれない。しかし、日本に存在する「牢屋」は、必ずしも「犯罪者」と認定された人が入る場所ばかりではない。なぜ、まだ「犯罪者」だと確定的に判明していない人の自由を奪うことが許されているのであろうか?また、そこでの生活は一体どのようなものなのであろうか?
「牢屋」のいろいろ
いわゆる「牢屋」は、正確には「刑事(収容)施設」と呼ばれる。刑事施設には、刑事司法手続、つまり①警察が犯罪現象を認知したところから始まる捜査段階、②その犯罪現象が事件として検察官により起訴されて刑事裁判が行われる公判段階、③裁判で確定した有罪判決で刑罰が言い渡された際の刑罰執行段階、それぞれの段階で用いられる刑事施設が存在している。③の刑罰執行段階で用いられるのが、おそらく最も一般的に「牢屋」として認識されている「刑務所」である。刑務所では、刑事裁判の判決で言い渡された刑罰のうち、懲役刑、禁錮刑、拘留刑が執行される(ちなみに、2022年の法改正で懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」という新たな刑罰に単一化され、今後数年以内に刑務所内の状況は大きく変わる可能性があるが、それはまた別の話)。
これに対して、①②の段階で用いられる刑事施設が、「警察留置場」と「拘置所」である。前者はその名のとおり警察に設置された警察所管のもの、後者は法務省所管の施設である。通常の事件で犯人として疑われた人、被疑者(新聞等ではやや広い概念として「容疑者」と呼ばれるが、法律上は「被疑者」が正確な呼称である)は、逮捕されると警察留置場に身柄を拘束されることになる。一部、警察ではなく検察が直接捜査を行う事件(脱税や政治家の汚職、背任や企業の横領・詐欺事件等の経済事件)の場合、検察が被疑者を逮捕するため、警察留置場ではなく拘置所に拘禁されることになる。
留置場と拘置所って何が違うの?—代用監獄の話
また、通常の事件で逮捕され、警察留置場に拘禁された人は、逮捕から48時間以内に検察官に事件が送られ、そこから24時間以内に検察官がその後も「勾留」という身柄拘禁を裁判所に請求するか否かを決め、裁判所が検察官の勾留請求を認めた場合、10日間(その後10日間の延長がありうる)の勾留が行われる。この勾留の場所は、本来、拘置所であるべきところ、現状ではその多くが(起訴前の勾留が終わり、起訴されて起訴後の勾留になるまでは)警察留置場で行われていることが常態化している。これは、刑事施設について規定した刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下、刑事収容施設法)3条と15条(またその前身の監獄法3条)で、留置場が拘置所の代わりに収容する施設になることを認めているためである(これを「代用監獄制度」という)。これは監獄法が作られた明治時代、まだ十分に拘置所を整備できなかったがゆえの応急処置として認められたものであったが(当時の国会答弁でもそのように説明されている)、ほぼ警察署の数(全国で約1,200)だけ存在する留置場に対し、拘置所は数が今もなお限られており(全国で8、支所98を合わせても100か所強)、被疑者の多くは代用監獄に起訴前の勾留中ずっと拘禁される現状にある。このことは、勾留中ずっと警察留置場で生活の全てを管理されながら捜査(主に取調べ)を受けることとなり、被疑者にとって代用監獄が冤罪の温床とも称される。また、拘置所においては一般的に個室に収容されることとなるが、警察留置場では複数の人が収容される集団室に拘禁されることが多くストレスの多い生活であること、食事も拘置所では調理設備があって温かい食事が摂れるのに対し、設備のない留置場ではお弁当等の冷えた食事しか摂れないこと等、心身ともに過酷な生活を強いられた中で捜査を受けることになるのである。
拘置所の生活なら問題ナシ?
そうとはいえ、拘置所の生活も決して一般社会の生活と同様ではありえない。これは全ての刑事施設で共通して、拘禁された人はまず個人名では呼ばれず、管理番号で呼ばれる。名前を剥奪されるのである。また、温かい食事や個室はあるものの、入浴は(多くても)夏場は週に3回・冬場は週に2回、日課と言われる1日のタイムスケジュールに沿って必ず生活しなければならず、食事以外は読書か書き物ぐらいしかできることがないまま、会いにきてくれた弁護人や親族等とアクリル板越しに会って短時間話す以外、夜9時の就寝時刻をひたすら待たざるを得ない生活となる。そして消灯後も、施設の安全管理上、完全には暗くならない部屋の中で眠れない夜を過ごすことも少なくない。刑務所に拘禁されている受刑者は、懲役刑であれば刑務作業を行うが、未決拘禁の人はそのような義務がないからである。外の社会で、スマホやネットがある中で1日を過ごすのとは全く違う時間の流れがそこにはある。真の退屈は、人(の精神)を殺しかねない。そこで、請願作業といって、刑罰でもないのに自ら申し出て作業を行い、最低賃金よりはるかに些少な作業報奨金と呼ばれるお金を受け取る人もいる。そのお金も、自由に好きなもの(書籍等)を買える訳ではなく、施設に出入りする業者から定価で購入せざるを得ないのである。
「犯罪者」かどうか決まってない人の拘禁はなぜ許される?
さて、ここで改めて冒頭の疑問に戻ってみたい。なぜ、まだ「犯罪者」だと確定的に判明していない人の自由を奪うことが許されているのであろうか。①②の段階での拘禁は、③とは異なり、まだ裁判で判決が確定していない人が拘禁されるため、「未決拘禁」と呼ばれる(対して③は「既決」と言われる)。刑事裁判は「犯罪者」であると疑われた人の行為について、証拠に基づいた判断を行う場所である。人間は神様の視点で真実を知ることはできない。たとえ現行犯逮捕の事件であったとしても、(それまでの経緯や故意等の内心の問題含めて)一体その事件において何があったのかを客観的に認定するためには、これを証拠として用いることが許されるような適正な証拠によって、人間が知ることのできる限りの事実を明らかにする必要がある。ということは、未決拘禁されている人は、そのような裁判で犯罪をしたということを確定されていない人なのである。
このような段階にある人は、たとえ疑われていようとも裁判で有罪判決が確定するまでは「無罪として推定されなければならない」という無罪推定原則があり、一般市民と変わらない、普通に生活する権利を有しているものと言える。ではそのような人々が拘禁されることが許されている理由は何なのであろうか。刑事訴訟法に規定された勾留の要件(同法60条)によれば、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があって、住所不定だったり、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあると疑うに足りる相当な理由があったりする時に、その後の刑事裁判が適正に行われることを確保するべく、やむを得ず許されうるものなのである。決して、裁判前から懲罰的に閉じ込めて、つらい生活を強いるために拘禁されている訳ではない。まして、その間の生活がつらすぎて、今その生活から逃げられるのであれば、やっていない犯罪も認めてしまおう…などと考えるようになるためでもないのである。 「犯罪者」として疑われ、起訴された後も長期間にわたって無実を争いながら未決拘禁生活を送る人は、かような毎日の中で、一体どのような想いを抱いているのか。刑事裁判、とりわけ有罪・無罪を争うような裁判には時間がかかる。もちろん、拙速にいい加減な裁判が行われるべきではない。しかし、その人の人生の貴重なひとときは、今日も刻一刻と刑事司法制度に削られている。
立命館大学教授・森久智江