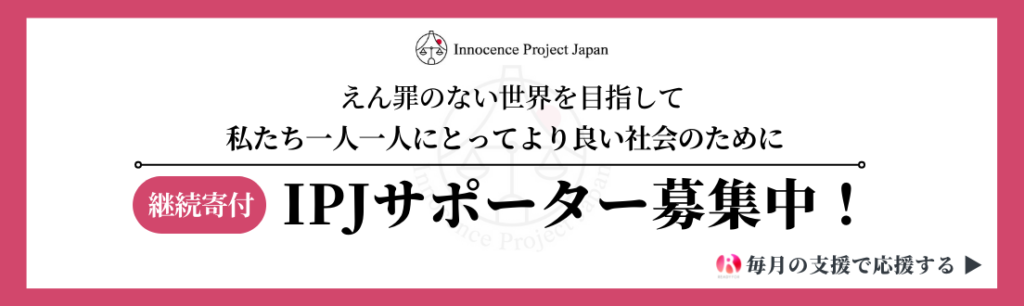龍谷大学 IPJ学生ボランティアは、6月3日に京都地方裁判所へ裁判傍聴に行きました。主に今年度新しく入ったメンバーが参加し、覚醒剤取締法違反の審理を傍聴しました。
今回の裁判までの経緯を簡単に説明します。被告人は過去にも覚醒剤を使用しており、ダルク(DARC)という更生施設に入所していました。それから2年が経過した頃、被告人は偶然、知り合いの現役の暴力団員と出会いました。そのとき、暴力団員から薬物を勧められ、仕返しを恐れた被告人は薬物を購入してしまいました。購入してから数か月は使わずに自宅に保管していましたが、友人が自宅に来た時にその場の流れで覚醒剤を使用してしまいました。以降、数回にわたり売人から薬物を購入しており、職務質問によって今回の事件が発覚しました。
薬物の売買が行われたのは、私が普段から利用する駅や大学の近くでした。よく知っている場所でそんなことが行われていたのかと驚きました。
薬物依存の怖いところは、2年間も断薬していても、1回の薬物使用で再び依存の症状が現れる依存性の強さだと思いました。そしてその症状に一番苦しむのは薬物を使用した本人だと思います。被告人は薬物を使用してはいけないことを理解していました。ダルクに入所して断薬のため努力していたと思います。それでもやめられない薬物というものは本当に恐ろしいとあらためて感じました。
被告人は覚醒剤の使用を認めており、自身の行いを反省しているようにみえました。 薬物依存症は、ひとりでは治すことは難しいものです。被告人は「断薬はひとりではできない。しかし仲間や施設のサポートがあればできる。」と述べていました。断薬には周りの人や更生施設の支援が必要です。また、この被告人のように暴力団などから脅されて薬物を購入してしまうことがあると思います。そういったことからどう身を守ればいいのか考えなければならないと思いました。
今回の傍聴で、今まで他人事のように思っていた薬物の存在を身近に感じることができました。さらに、薬物依存を克服する難しさも同時に知りました。〔法学部2回生〕
私は裁判傍聴は2回目ですが、法廷に入った瞬間から緊張感があり、スッと背筋が伸びる感じがしました。裁判は粛々と行われ、ドラマで描かれているものとは違い淡々と進められていくのだなと感じました。弁護士や検察官は被告人に対して、様々な視点から質問するのだなと思いました。また、傍聴に来ている人が多く、傍聴席が満席になっていたので珍しいことだなと思いました。また裁判傍聴に行ける機会があれば参加したいなと思います。〔法学部2回生〕
傍聴後は京都地裁の向かいにある京都御苑を散策しました。昼食は弁護人の先生(龍谷大学名誉教授・福島至先生)とご一緒し、刑事裁判について色々とお話を伺いました。

*当サイトの内容、テキスト、画像等の転載や複製を禁じます。