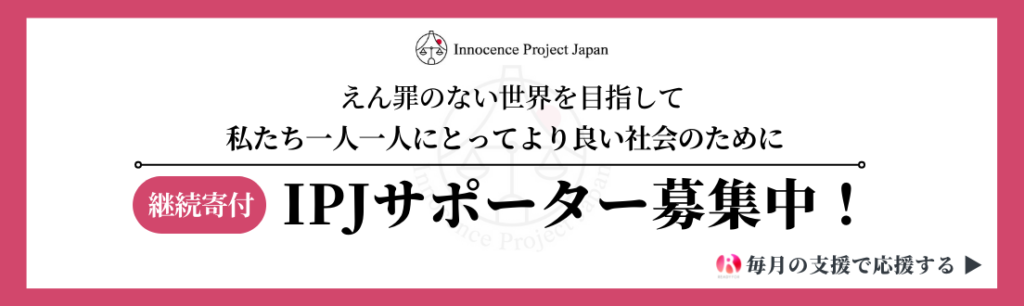大阪拘置所は、近畿2府4県の刑事事件で検挙された被疑者・被告人について、逃亡や証拠隠滅を防ぐために一時的に収容されています。被疑者以外にも死刑確定者や、拘置所内の掃除や洗濯などに従事する、一定数の既決受刑者が収容されています。
刑事事件には、被疑者・被告人の刑が確定するまでは無実の人と同じ扱いをしなければならないとする考え方があります。無罪推定原則です。そのため、拘置所に収容されている被疑者・被告人には、ある程度の自由が認められています。差し入れや服装の規定は、受刑者より融通が利きます。
また、前述のとおり、一定数の受刑者たちが収容されていますが、更生・社会復帰のために就労支援システムが整っています。2025年6月から、懲役刑と禁錮刑が拘禁刑に一本化されるという刑法の改正が施行され、受刑者のニーズに合わせてプログラムが20以上に分かれていたり、特別コースも新設されるようになったりしています。円滑な社会復帰のために、ここまで多くのプログラムがあることに驚きました。拘禁刑は新しくできたものですが、これから社会復帰する人たちの生き方にどのような影響があるのかはわからない部分が多いため、今までのプログラムより、さらに効果が出てほしいと感じました 。
大阪拘置所では、施設見学と刑務官の方々とグループワークをすることができました。グループワークでは、刑務官の仕事内容や、拘置所内に収容されている人たちのルールについて、いくつかの質問をしました。刑務官は常に規則に沿った行動が求められるので、厳格な人が多いと思っていましたが、そのようなことはありませんでした。施設見学で思ったことや、事前に考えてきた質問をたくさんしましたが、気さくに冗談交じりに楽しく話してくださり、緊張せずに話せました。
その中で、防犯カメラ入り口にしかないことを疑問に思い、質問をしました。答えは、防犯システムがあり、異常があれば職員が即座に対応できるようにしているとのことでした。そのため、刑務官は当然ですが、24時間体制で仕事をしています。武術の鍛錬もされているようでした。それでも、気さくに接してくれた刑務官はとても強い人だと思いました。
施設見学の時には色々な内部設備について案内いただきました。その中で、施設や設備に様々な工夫がされていて驚かされることが多数ありました。
大阪拘置所の中にはCTルームや人口透析機があるなど、高度の医療器具が整っていること、診察室がいくつもあり、病院のような医療体制が確立されていることに驚きました。見学した収容室では、棚の角が丸く、放物線を描く形にすることや、短いタオルしか手に入らないようにして自傷行為や首吊りを防いで自殺させないようにしていました。また、収容室の窓が少し黒くなっており、廊下を見れるようにしている一方で、反対側にある部屋の様子を見えなくすることで、被収容者同士のコミュニ―ケーションや合図をとれなくしていました。屋上には運動場が設置されており、上から監視できるように上に通路があります。そのため、上からでは死角になっているところがありました。対策として、受刑者が何かしているのを見逃さないために入り口から30㎝以上離れたところから活動するようにさせていました。このように様々なリスクを回避していることに衝撃を受けました。
大阪拘置所の中では、設備を整え、更生するための機会を失わせないようしたり、被疑者・被告人の扱いをなるべくよくするために制度の拡充をしたり、職員の仕事の変化があったりするようでした。日本の刑事事件では、上記で挙げた、無罪推定の原則があります。そのため、一般の人からしたら、「悪い人」や「悪いことを行なった恐れがある人」にそこまでの処遇が必要なのかは疑問になるかもしれません。でも、人としての保護すべき権利や防御権などは、被疑者・被告人はもちろん、受刑者にも認められています。
しかし、実際には、被疑者・被告人(未決)は、ニュースでまるで犯人のように取り扱われてしまいます。さらに問題なのは、疑いが晴れて外に出れても「実は、やったのでは?」と、疑われてしまい、偏見を持たれてしまったり、社会人なら長期間拘束されてしまうため、仕事に影響が出てきてしまうことです。このような長期間の収容は、未決の人にとっては生活に多大な影響を出してしまいます。また、前科・前歴がある人に対して偏見の目が持たれてしまうのも大きな問題点です。
近年、刑事訴訟法の改正が盛んになっており、未決の人が長期間収容されないような制度へと変化して行ってほしいです。また、報道の在り方に関してもまだ被疑者・被告人の段階で犯人のように扱ってしまう現状は変わってほしいと思いました。一つの報道で、他人の生活に大きな影響を与えてしまう恐れがあるため、慎重になってほしいと感じました。
受刑者についていえば、上記のような制度や支援があっても、再犯してしまう人がいるのも事実です。そのため、一般の人からしたら、犯罪を犯した人は、「また、するのでは?」と、怖さを感じて、偏見を持ってしまうのは無理もない話なのも事実です。 しかし、このような制度や周りからの支えで更生できる人がいるのも事実です。これから上記のプログラムの導入のような様々な改革や工夫が進み、更生や社会復帰がしやすくなり再犯率が下がって偏見を持たれにくい社会になってほしいと思いました。
【甲南大学2回生 貴志純宇】
===========
大阪拘置所に参観に行きました。
最初に施設内の見学をしました。運動場、食事を作る場所、受刑者の方が収容されている部屋、病気にかかった際に検査をする場所などを見ました。刑務官の方が誘導してくださり、説明してくださったので、未決被拘禁者、死刑囚、受刑者の方の生活を想像しながら施設見学ができ、とても勉強になりました。
私は、1回生のときに受講した刑事法入門の授業で、未決被拘禁者や受刑者の方の居室、運動場を写真でみました。その時は一般的な部屋の大きさなのかなと感じたのですが、実際に入ってみるととても狭く感じました。
運動場では、太陽の光があたると言っても天井に鉄格子のようなものがあって、開放的に運動できるとは思えなかったです。
最後に、実際に拘置所で働かれている職員の方と質疑応答の時間がありました。
施設見学で運動場をみた際に、壁にあった運動のルールで「運動をする者は首にタオルをかけてはいけない」と書かれており、疑問に感じたことについて質問しました。答えは、首にタオルをかけていると被収容者が自殺をしてしまうおそれがあるからというものでした。
ニュースで留置施設の中での受刑者の方が自殺をしてしまったというのを聞いたことがあります。対策をきちんと行っているということを実際に働かれている方からお聞きすることができてよかったです。
今回の学びを通じて後期以降の大学の勉強をより一層頑張りたいと思いました。
【甲南大学2回生冨田明里】